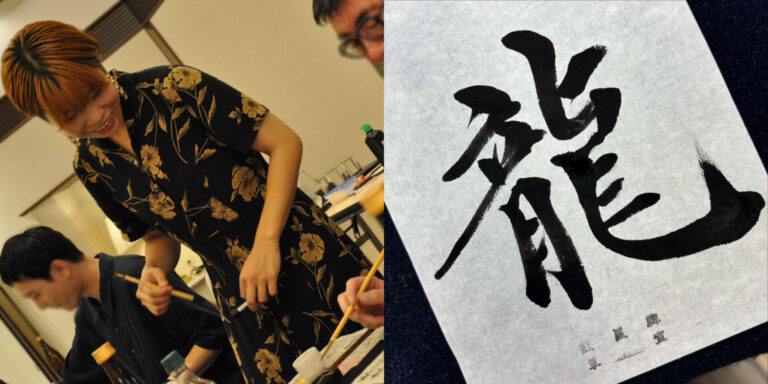働く日々に“余白”を設け、よりよい生き方を模索する人をインタビューする連載「人生に必要な“余白“を考える」。今回は「ぼーっとする大会」の日本大会をプロデュースする株式会社VIS代表取締役・古井敬人(ふるい・けいと)さんにインタビューを実施した。

古井 敬人(ふるい・けいと)さん
ぼーっとする大会プロデューサー/株式会社VIS代表取締役
湘南工科大学卒業。2023年、大学4年次に株式会社VISを創業。創業後、「ぼーっとする大会」を日本で初開催。地上波28番組での放映を記録し、ムーブメントを作る。現在は「ぼーっとする大会」を中心に、ウェルネス事業に取り組む。
「ぼーっとする大会」はその名の通り、何もせず、ただただぼーっとする大会。
自分の職業や立場を象徴する格好で参加する芸術点と90分間の心拍数の変動を測定する技術点の2つで審査され、一番得点の高い人が、一番ぼーっとできた人として優勝できる。2014年に韓国で始まり、オランダや台湾など世界6ヵ国以上で開催されている。
この大会が日本で開催されることを知ったとき、「ぼくでも優勝できるのではないか?」と思った。昔からぼーっとすることが好きだったからだ。
晴れた日に公園のベンチに座って、ただただぼーっとする。その時間はとても贅沢な気がして、心が満たされていた。けれど、忙しさにかまけて大会に参加することはなく、時は流れてしまった。
2024年10月、日本で2回目の「ぼーっとする大会」が開催されたというニュースをテレビで観て、「この大会を主催している人に話を聞いてみたいな」と思った。
なぜこのような大会を日本でも開こうと考えたのだろう。大会を通じて社会に何を伝えたいのだろう。ぼーっとすることの価値とはなんだろう。詳しくお話を伺った。
何もしないことの価値
──韓国発祥の「ぼーっとする大会」が2023年に日本で初開催されました。2024年には大阪や福岡などで予選大会も開催され、広がりをみせていますね。テレビ番組でも放映されましたし、SNSでも注目を集めています。
2023年の初開催の際には、ぼくはまだ大学4年生でした。海外で有名な大会だったとはいえ、いち大学生の自分に名だたる大企業や著名人が協力してくれ、ここまで大きなムーブメントになるとは思ってもみませんでした。
現代にはコンテンツが溢れていますよね。その中で何もしないこと、ぼーっとするだけの大会がこれだけ注目されたのは、ぼーっとしたくてもできない人が多いからなんだと思うんです。
多くの人が忙しい毎日を送り、多くのストレスを抱えている。何もしたくなくても、無駄な時間のように思えて、結局何かをしてしまう。だからこそ、ぼーっとするだけのこの大会は、多くの人の目に止まったのかなと考えています。
──参加者は、日常生活ではなかなかぼーっとできないからこそ、大会でぼーっとしようという思いの方が多かった。
そういう思いを抱えて参加くださる方が半数ぐらいで、2割は「興味本位で」とか「友達に誘われて」とかさまざまな理由です。残りの3割は、ぼくも意外でびっくりしたのですが、本気で優勝したいと思って参加してくださる方々なんですね。
それだけ多いのは、日本大会で優勝すると、世界大会への切符を手に入れることができるからだと思います。誰しもが参加できて、かつ、誰しもが優勝の可能性がある。日本代表になれるかもしれないし、世界チャンピオンになれるかもしれない。
そのように誰しもが主役になれるコンテンツは世の中にはあまりないので、チャンスだと思う人もたくさんいたのだと思います。
──参加者からはどのような感想がありますか?
「唯一無二の時間だった」と言っていただくことが多いです。やはり日常生活で90分間何もしないでいることは基本的にないと思うんですよね。
だからこそ、ほとんどの人が初めての体験で、「日々の生活の仕方を改めて考え直す機会だった」「時間の使い方や身を置く環境について、もう1度考え直そうと思った」とぼーっとすることへの価値を見出すような感想が多いです。
──古井さんはぼーっとすることの価値とは、どのようなものだと思われていますか?
そもそもぼくたちはぼーっとすることには、2種類あると考えています。
1つ目がマインドブレイキング。これは何も考えず、頭を空っぽにすることで、心を休める状態です。2つ目がマインドワンダリング。空想に耽り、何かを想像したり考えたりすることで着想を得るような状態です。
ぼーっとすることの価値は、どちらのぼーっとすることなのかによって変わってくると思います。
マインドブレイキングであれば、左脳を休めることでリラックス効果を得られますし、マインドワンダリングであれば右脳を働かせて、クリエイティビティを高めることにつながります。もちろんどちらか一方だけではなく、両方の価値を感じる場合もあるはずです。
最近は、右脳も左脳もフルに使っている経営者の方々を対象に、ぼーっとする経営者交流会といった新しい試みも行っています。
「楽しそうに生きている大人」に憧れて
──古井さんは「ぼーっとする大会」のことをどうやって知ったんですか?
起業家の先輩から教えていただいて知りました。もともとぼくは教師になりたくて大学で勉強していたので、起業しようと思ったものの、何の事業をしようか全く決まっていなかったんです。
──教師を目指していたんですね。
中学2、3年生のときの担任の先生がぼくの周りにいる大人で唯一「楽しそうに生きている大人」だったんですよね。
ぼくは小さなころから「大人って大変そうで、楽しくなさそうだな」と思っていたんですけど、先生はいまを全力で、未来にワクワクしながら生きている人でした。
だから教師になりたいというよりかは、その恩師みたいな大人になりたくて同じ道に進もうと思ったんです。恩師と同じ大学の同じ学部で、同じ免許を取得しようとしていました。
──すごい!そこまで同じにしていたんですね。でも、教師とは違う道へ進むわけですよね。
教育について学べば学ぶほど感じたのは、学校で教えられることと社会に出て求められることに物凄くギャップがあるということでした。昭和時代だったら正解だったかもしれない教育のあり方が、令和になっても変わらずに残っていると思ったんです。
それをいち教師が変革していくことはものすごく難しい。それならもっと社会に新しい価値を提供していくような道を考えてもいいかもしれないと、起業することを決意しました。
──そこから起業家の先輩に「ぼーっとする大会」のことを教えてもらったわけですよね。教育事業をやろうとは思わなかったんですか?
昔から起業を志していたわけではなかったので、全く知識もスキルもなく、とにかくできることからやろうと思ったんです。大学時代、BBQとか飲み会とか、イベントと呼んでいいかもわからないぐらい小さいことですけど、よくイベントを開いていたんですね。
これは恩師から「大学時代にイベントをたくさん開いていて、その経験が学級運営にめちゃくちゃ役立っている」という話を聞いたからでした。教育指導要領や教育関連の書籍からでは学べない経験が得られると。
だから起業を志してからは、それまでよりも少し本格的なイベントをやってみようと思って、アーティストを呼んで音楽ライブを開いたり、画家やデザイナーを呼んでライブペイントを行ったりしていました。
でも事業的にはうまくいかず、どうしようと悩んでいる時に「ぼーっとする大会」のことを教えてもらったんです。
世界を5分間止める
──「ぼーっとする大会」のことを知って、すぐに日本でもやろうと思われたんですか?
最初は安直な理由で、世界で話題になってるこの大会を日本でも開いたら自分の実績になるだろうと思っていました。
でも、開催許可を取るために発起人である韓国の女性画家・woopsyang(以下、ウプスヤン)さんと話して感銘を受け、一緒にこの大会を広げていきたいなと強く思ったんです。
「ぼーっとする大会」はイベントとして捉えられることが多いんですけど、参加型アートなんですね。せわしなく動く社会の中に、何もしない集団が現れることで、「何もしないでいることは無価値なのか?」を問う作品なんです。
だから、大会に応募してもらったとしても全員が参加できるわけではありません。性別や年齢、職業がバラバラになるように運営側が意図的に選んで参加者を決めています。
また大会当日の服装も、なるべく自分がいつも働いている格好で参加してもらう。働くという行為はぼーっとする行為の対極にあると思うんですね。
だからあえて、働いているときの姿で参加してもらい、それを芸術点として審査するようにしています。
──アート作品とは思っていなかったです。
彼女は芸術家の活動をしてきた中で、精神的な病気にかかってしまったことがあったそうなんです。でも、なかなか休むことができなかった。
韓国も成長や効率性を重視するような社会で、自分だけが休むわけにはいかない、止まれないと思っていたみたいなんです。
そこで思いついたのが「ぼーっとする大会」で、自分を休ませてあげたいから周りも巻き込もうと。最終的には「世界を5分間止めたい」という思いで、彼女はこの活動をしているんです。
──世界を5分間止める。
時間を止めることはできないので、できるだけ動きを止める、何もしないでいるという意味でぼくは捉えています。世界が5分間止まったらと想像してみると、その時間はものすごく平和になるんじゃないかと思うんですよね。
戦争をはじめとする社会問題、身近で起きてる喧嘩やちょっとしたいざこざも、5分間立ち止まってみる。世界の約80億人が、一斉に何もせずにぼーっと過ごしてみる。そして、今の自分のあり方や状況を考えてみる。それができれば、ぼくたちが忘れてしまっている大事なことに気づけるんじゃないか。
そう思って、ウプスヤンさんと一緒にこのアート作品を広げていきたいなと思いました。
幸せそうな大人を増やす
──5分間世界が止まったら確かに平和な瞬間が訪れるのかもしれませんね。
平和だし、おそらく幸せを感じるというか、幸せに気づける人も多いんじゃないかなと思うんですよね。せわしなく生活を送っていると見過ごしてしまいがちな幸せもあるんだと。
なので、この大会を広げていくことで、社会の幸福度が上がっていけばいいなとも考えています。幸せに過ごす人が増えれば、それこそ教育に結びついていくと思うんですよ。
──どんなふうに教育に結びつくんでしょう?
「幸せそうじゃない大人」がありふれた社会って教育にとって一番よくないと思うんです。しんどそうな生き方をしている大人を見て育った子どもが、未来に希望を持つことはとても難しい。
ぼくの場合はありがたいことに恩師との出会いがあったからよかったのですが、そういう出会いもなく、大人になるのが嫌だなと思いながら生きている子どもはたくさんいるはずです。
もちろん人生には楽しくないこと、つらいこともたくさんあるので、しんどくなるときもあると思うのですが、つらいいことも自己成長と結び付けることで、できる限り楽しそうな大人とか、幸せそうな大人とか、そういう人が増えてほしい。
今を全力で生きて、未来にワクワクする大人が増えれば、自ずと子どもたちへプラスの影響を与えるんじゃないかと考えています。
──大人がもっと幸せそうに生きる姿を見せていくべきだと。
もちろん今の大人たちが悪いというつもりはありません。常に競争を求められ、大量生産、大量消費が正解で、せわしなく動く社会があったからこそ、ぼくたちが受け取れている恩恵もたくさんあります。それは本当にありがたいなと思う一方で、徐々に時代が変わってきていますよね。
走り続けてきたけれど、一旦立ち止まってみるのもいいかもしれない。人生に余白を設けてみることも大事かもしれない。
そういう価値観が徐々に社会に浸透してきています。バトンをつないでもらったとぼくは思っているので、それを次世代につないでいけるようにしたいですね。
──とはいえ、なかなか忙しくてぼーっとなんてしていられないという人はまだまだ多いと思います。「ぼーっとする大会」以外の日常でも、ぼーっとするためにはどんなことが必要だと思われますか?
ぼく自身もぼーっとする時間を取れないときもあるので、非常に難しい質問ですね。ただひとつ言えるのは、ぼーっとする時間が大事というよりかは、心に余裕があることが大事なのかなと思っています。
なかなかぼーっとする時間が取れなくても、何かトラブルがあったときに一旦立ち止まれるとか、誰かと関わるときに余裕を持って接しようとか、そういう意識が持てればいいと思うんです。
だからコーヒーを飲むときにでも、1分でもいいから何もせずに、ただコーヒーを味わって深呼吸してみる。そんなところから始めて、徐々にぼーっとする時間を設けてみればいいのではないかと思います。
一見無駄なことのように思える「ぼーっとする」行為。しかし、古井さんのおっしゃるように、世界平和につながるかもしれないし、自分の幸福度をあげることにつながるかもしれない。そんな可能性を秘めた、大事な行為なんだということに気づけた。
少しずつでもいいから、ぼーっとする時間を取りたい。時間をとることが難しくても、余白を取ることは人生において大切なことなんだという意識だけは、忘れないようにしたい。
ソラミドmadoについて

ソラミドmadoは、自然体な生き方を考えるメディア。「自然体で、生きよう。」をコンセプトに、さまざまな人の暮らし・考え方を発信しています。Twitterでも最新情報をお届け。みなさんと一緒に、自然体を考えられたら嬉しいです。https://twitter.com/soramido_media
取材・執筆

ああでもない、こうでもないと悩みがちなライター。ライフコーチとしても活動中。猫背を直したい。
Twitter: https://twitter.com/junpeissu